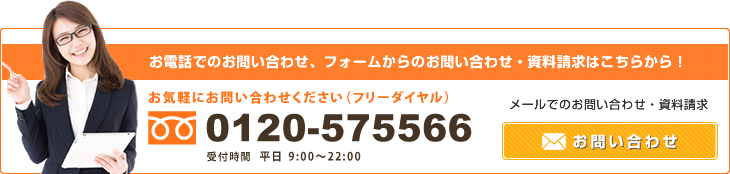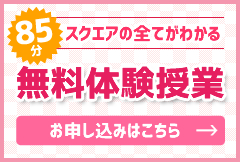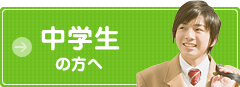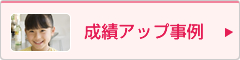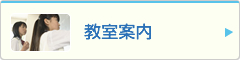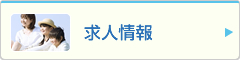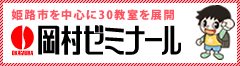- 岡ゼミ個別スクエア
- 岡ゼミ個別スクエア・スタッフブログ
冬季講習始まりました
エントリー投稿日:2025/12/27
こんにちは、増位校個別の安福です。
2025年も残すところあと数日となりました。
皆さんは、どんな1年でしたか?
増位個別では冬季講習真っ只中、14時から22時まで毎日たくさんの生徒が
授業を受けています。
中3生は推薦入試の切符を手に入れた生徒が多く、推薦入試対策で、
早速小論文の練習を始めています。
皆、小論文を書いたことが無いため、何から始めていいか分からず、
国語担当の講師と一緒に、自分の夢や長所・短所等、話し合いながら
細かく自己分析を行っています。
2月の推薦入試までまだ1ヶ月以上ありますが、早めに取り組んで
しっかりと自信をつけて入試に挑んでほしいと思います。
講師たちもいろんな資格を取るため、大変努力しています。
(看護師・国家公務員・教師・弁護士)
とても頼りになる講師たち、その姿勢が生徒たちにいい刺激を与えていて、
教室へ楽しく通ってくれている生徒が多いです。
中学生たちも、将来は個別講師として増位個別へ戻ってきてくれるかな・・・
私は、そのような事を毎年願っています。
増位校個別 安福
2025年も残すところあと数日となりました。
皆さんは、どんな1年でしたか?
増位個別では冬季講習真っ只中、14時から22時まで毎日たくさんの生徒が
授業を受けています。
中3生は推薦入試の切符を手に入れた生徒が多く、推薦入試対策で、
早速小論文の練習を始めています。
皆、小論文を書いたことが無いため、何から始めていいか分からず、
国語担当の講師と一緒に、自分の夢や長所・短所等、話し合いながら
細かく自己分析を行っています。
2月の推薦入試までまだ1ヶ月以上ありますが、早めに取り組んで
しっかりと自信をつけて入試に挑んでほしいと思います。
講師たちもいろんな資格を取るため、大変努力しています。
(看護師・国家公務員・教師・弁護士)
とても頼りになる講師たち、その姿勢が生徒たちにいい刺激を与えていて、
教室へ楽しく通ってくれている生徒が多いです。
中学生たちも、将来は個別講師として増位個別へ戻ってきてくれるかな・・・
私は、そのような事を毎年願っています。
増位校個別 安福
勉強=魔法?
エントリー投稿日:2025/11/29
中学生の英語教科書ではよくアニメが話題になっています。その際にはよく生徒たちにどんなアニメが好きか尋ねます。私は、小学生のころからアニメがとても好きで、今でも長期の休みにはリメイク作品から最近のものまで一気見して楽しんでいます。なので、たまに生徒たちとアニメの話題で盛り上がるときがあります。ただ、一つだけ苦手なジャンルがあります。それが、ここ数年流行りの異世界ものや、都合よく魔法や異能でなんでも解決してしまうファンタジーアニメで、まったく好きではありませんでした。一方、子供たちは大好きなんですよね。私には、なんだか現実逃避にしか思えず、面白さがよくわからなかったのです。「私も~だったらなぁ」と他人の能力、しかも現実にはあり得ないものを羨むだけで、何が変わるのだろうと、懐疑的に見ていました。
でも、最近、まわりの子供たちの様子を見て考え方が変わりました。子供たちからすると、現実にはできないことを「体験できる世界」は、自分の中に新しい考え方を生み出すきっかけになるのだと気づきました。魔法を使って困難を乗り越える登場人物を見ると、ただの逃避ではなく、手段(魔法や異能)をどう使うかで「結果が変わる」という考え方が描かれていることに気づきました。
そこでふと思ったのは、魔法は物語の中での手段であるように、勉強も現実世界での手段だということです。魔法があっても、登場人物が何も考えずに使うだけでは成長できません。勉強も同じで、点数を取るためや高校に進学するためだけにするのでは、意味が限られてしまいます。大事なのは、勉強で得た知識や経験をどう活かすか、どう行動するかです。魔法=勉強をうまく使えば、自分の力や未来を変えることができるのです。
ファンタジーの物語から学べることは、「手段の使い方次第で結果が変わる」という大切な考え方です。勉強も魔法も、ただの道具(手段)ではなく、自分を成長させるチャンスになるものです。そして、その道具は手入れをしておかないと、いざというとき、つまりチャンスを感じた時に使い物にならないことも忘れてはいけませんね。
青山校個別/新飾磨校個別 矢内
でも、最近、まわりの子供たちの様子を見て考え方が変わりました。子供たちからすると、現実にはできないことを「体験できる世界」は、自分の中に新しい考え方を生み出すきっかけになるのだと気づきました。魔法を使って困難を乗り越える登場人物を見ると、ただの逃避ではなく、手段(魔法や異能)をどう使うかで「結果が変わる」という考え方が描かれていることに気づきました。
そこでふと思ったのは、魔法は物語の中での手段であるように、勉強も現実世界での手段だということです。魔法があっても、登場人物が何も考えずに使うだけでは成長できません。勉強も同じで、点数を取るためや高校に進学するためだけにするのでは、意味が限られてしまいます。大事なのは、勉強で得た知識や経験をどう活かすか、どう行動するかです。魔法=勉強をうまく使えば、自分の力や未来を変えることができるのです。
ファンタジーの物語から学べることは、「手段の使い方次第で結果が変わる」という大切な考え方です。勉強も魔法も、ただの道具(手段)ではなく、自分を成長させるチャンスになるものです。そして、その道具は手入れをしておかないと、いざというとき、つまりチャンスを感じた時に使い物にならないことも忘れてはいけませんね。
青山校個別/新飾磨校個別 矢内
受験生へこれからの勉強についてのアドバイス
エントリー投稿日:2025/11/03
こんにちは。岡村ゼミナール福崎校個別教室の横野です。
いよいよ11月になり、入試まで日をきりました。中3生におかれましては、志望校に向け、2学期期末テストを見据えて、気の抜けない日々かと思います。
福崎校の個別生も、顔つきが少しずつ変わってきました。
志望校合格に向けて、学習に取り組んでください。
横野から、アドバイスをお送りいたします。
①一日の学習計画を立てる。
1科目の学習時間は学校と同じく50分にして、間に5分の休憩をいれるようにしてください。また、学習する科目は、得意な科目と苦手な科目両方を組むようにしてください。どちらかにかたよってしまうと、やる気がなくなる原因となります。また、最後にその日に学習したことの振り返りをする時間を10分でいいので作ってください。
②分からないことは、学校や塾で質問する
分からないことで悩んでいると、あっという間に時間が過ぎてしまいます。解説があれば、それを見て解き方を覚え、解説がない、もしくは解説を見ても分からない場合は、学校や塾の先生に必ず質問してください。
③不安な気持ちがあればだれでもいいので相談する。
勉強方法や進路について不安があるが、親には相談しづらいこともあるかと思います。そういう時は、友達や学校の先生、塾の先生に相談してみてください。一人で抱え込まないようにお願いします。
④最後は体力勝負
受験勉強は体力と精神力を使います。体調が悪いと効率よく学習できませんので、出かけるときはマスクをして、外から帰ったら手洗い・うがいをし、体調管理に努めてください。
このブログを見ている受験生全員、志望校に合格できるよう、祈っています。
岡村ゼミナール福崎校個別教室責任者 横野友紀
いよいよ11月になり、入試まで日をきりました。中3生におかれましては、志望校に向け、2学期期末テストを見据えて、気の抜けない日々かと思います。
福崎校の個別生も、顔つきが少しずつ変わってきました。
志望校合格に向けて、学習に取り組んでください。
横野から、アドバイスをお送りいたします。
①一日の学習計画を立てる。
1科目の学習時間は学校と同じく50分にして、間に5分の休憩をいれるようにしてください。また、学習する科目は、得意な科目と苦手な科目両方を組むようにしてください。どちらかにかたよってしまうと、やる気がなくなる原因となります。また、最後にその日に学習したことの振り返りをする時間を10分でいいので作ってください。
②分からないことは、学校や塾で質問する
分からないことで悩んでいると、あっという間に時間が過ぎてしまいます。解説があれば、それを見て解き方を覚え、解説がない、もしくは解説を見ても分からない場合は、学校や塾の先生に必ず質問してください。
③不安な気持ちがあればだれでもいいので相談する。
勉強方法や進路について不安があるが、親には相談しづらいこともあるかと思います。そういう時は、友達や学校の先生、塾の先生に相談してみてください。一人で抱え込まないようにお願いします。
④最後は体力勝負
受験勉強は体力と精神力を使います。体調が悪いと効率よく学習できませんので、出かけるときはマスクをして、外から帰ったら手洗い・うがいをし、体調管理に努めてください。
このブログを見ている受験生全員、志望校に合格できるよう、祈っています。
岡村ゼミナール福崎校個別教室責任者 横野友紀
正念場
エントリー投稿日:2025/10/18
こんにちは。曽根校の大谷です。
曽根校では地域の祭りに合わせて授業日を変更し
10/14(火)を休塾日としました。
中間テストが終わり、祭りが終わり、
一息つきたい所ではありますが
今が正念場です。
今頑張ることが周りと差をつけるチャンスです。
期末テスト前にはテスト勉強をとことんやりますから
受験勉強として復習に充てる時間は今しかありません。
1日1日を無駄にせず後悔のないように過ごしましょう。
曽根校 大谷
曽根校では地域の祭りに合わせて授業日を変更し
10/14(火)を休塾日としました。
中間テストが終わり、祭りが終わり、
一息つきたい所ではありますが
今が正念場です。
今頑張ることが周りと差をつけるチャンスです。
期末テスト前にはテスト勉強をとことんやりますから
受験勉強として復習に充てる時間は今しかありません。
1日1日を無駄にせず後悔のないように過ごしましょう。
曽根校 大谷
運動と記憶
エントリー投稿日:2025/10/09
こんにちは。A-Plus西脇校 中元です。
長い残暑が続き、それもようやく収まったようで過ごしやすくなりました。
こちらの地区ではこれから運動会・体育祭の時期で、練習に力が入っているようです。
さらに、中間テストが近づいています。
勉強漬けで疲れてしまったという人は、軽い運動を挟んで気分転換をしてみてはいかがでしょうか。
運動すると記憶力がよくなるという研究結果もあるようです。
脳の記憶を司る海馬が運動によって活性化すること、脳に酸素や栄養が供給され、神経伝達物質の分泌が増えることで記憶力が向上するようです。
運動と勉強のいずれも行いやすい季節なので、積極的に取り組んでいけるといいですね。
勉強前の軽い運動も効果的だということなので、お試しください。
さて、岡村ゼミナールでは秋の2週間体験を行っています。
個別指導と集団授業をそれぞれ1週間の体験授業を受けられます。
分からないところは早く克服して、将来の夢に向けて頑張りましょう。
A-Plus西脇校 中元
長い残暑が続き、それもようやく収まったようで過ごしやすくなりました。
こちらの地区ではこれから運動会・体育祭の時期で、練習に力が入っているようです。
さらに、中間テストが近づいています。
勉強漬けで疲れてしまったという人は、軽い運動を挟んで気分転換をしてみてはいかがでしょうか。
運動すると記憶力がよくなるという研究結果もあるようです。
脳の記憶を司る海馬が運動によって活性化すること、脳に酸素や栄養が供給され、神経伝達物質の分泌が増えることで記憶力が向上するようです。
運動と勉強のいずれも行いやすい季節なので、積極的に取り組んでいけるといいですね。
勉強前の軽い運動も効果的だということなので、お試しください。
さて、岡村ゼミナールでは秋の2週間体験を行っています。
個別指導と集団授業をそれぞれ1週間の体験授業を受けられます。
分からないところは早く克服して、将来の夢に向けて頑張りましょう。
A-Plus西脇校 中元